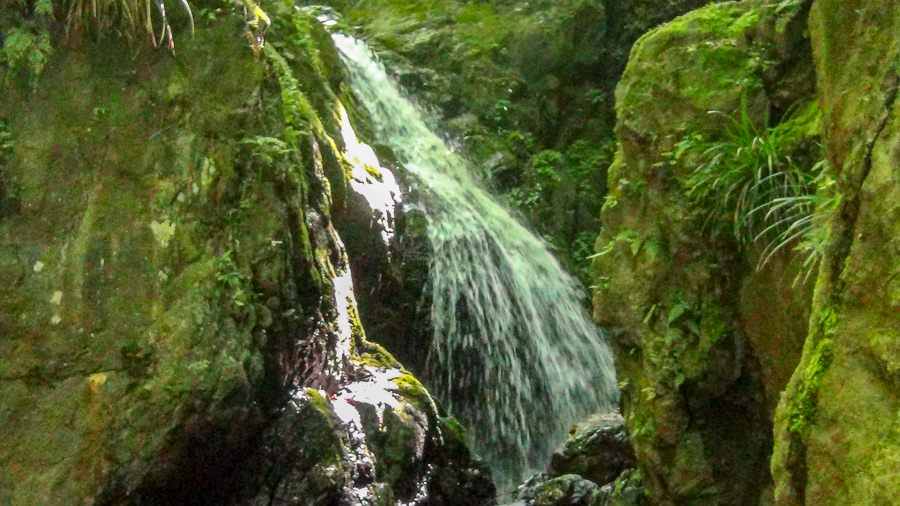滝の記憶
1人メンバーが去った
2016年紀伊半島3日目。
2人で向かったのは大峰山脈、
吉野川水系の矢納谷でした。
矢納滝の位置↓
滝の記録
訪問日 2016年5月5日
活動の形態:上級滝巡り&沢登り(2名)/レンタ
装備:沢タビ, 7mm30m×1
感動度(昇竜):かなり
所在地:奈良県 吉野郡 川上村 上多古 / 吉野郡 天川村 洞川
①奈良の谷
どちらかと言えば
沢要素が強かったこの日の活動。
奈良県で初めての沢登りです。
②矢納滝
鳴川山林道は途中から荒れ始めるので、
終点まで徒歩16分ぐらいの
駐車スペースっぽい所でストップ。
林道歩きの途中では
2本の滝を見ることができます。
終点から山道になりますが、
分岐で右に行ってしまうと、
上多古川本谷のほうに行ってしまいます。
左へ梶を取るとすぐに見える勢いの良い滝。
斜面を下って行って滝壺へ。
【矢納滝 15m】

瀑水が落ちきるその場所に岩が有り、
『バチバチバチバチバチ!!!』と、
けたたましい音が鳴り響いています。
道へ戻り滝を巻いてから入渓しました。
③岩を越える
入渓してからしばらくで、
緩いC字状に弧を描く滝(8m)が。

なかなかの美瀑でした。
ここは左岸から通過します。
この後は岩の隙間を
通過していくような箇所が多くなり、
大岩にかけられた、
グラグラするハシゴの通過は、
ヒヤリとしました。

(下り)
この辺りは、左岸の昔の道は
崩壊してありませんので、
この次の滝へ行くには、
途中で沢沿いを進み、
このハシゴを越えないとなりません。
④昇る竜
ハシゴを越えてしばらく進んで現れるは、
この谷一番の大滝になります。
【昇竜の滝 40m】

この滝は日本の滝100選の、
平均的な水準の規模感と威容を誇り、
滝名もまさに姿を捉えている一本です。
ちょいと危険ですが、
右下に見える丸太の木を越えれば、
滝に接近できます。

この滝だけでも十分に訪瀑価値があります。
⑤読み
高巻きは少し戻って
左岸の緩いルンゼから。
その後のルートの意見は別れましたが、
僕の読みが合っていて大高はせずに、
昇竜に近づいてから直上して
正規ルートに合流。
穏やかな渓相になってから谷におりますが、
戻ってみた落ち口が昇竜なのか2段15mなのか
わかりませんでした。
しかしこの後2段15mは現れなかった+、
よくよく考えたら距離的にも、
一緒に巻いてしまったんだと思います。
その後はやや右岸沿いが多くなり、
連瀑帯を巻き気味に越えていきます。
一部足場が悪かった気がします。
⑥赤い両門
するとその不安定な右岸沿いに
滝直下が赤茶けた、
落差のある滝が見えてきます。

立派な滝でこれが「赤ナメクチの滝」
なのかと思いました。
しかし実際は支流の30m直瀑で、
赤ナメクチの滝は本流として奥に掛かり
両門滝を形成。

唯一邪魔なのが谷沿いに伸びるワイヤーで、
これはこの場でもけっこう悪目立ちします。

それでもかなり安息の地で
居心地は良かったです。
⑦あと一歩
この谷には極端な難所はありませんが、
地味な難所は3,4点散在していて、
ちょっと前の、
高巻きのルーファイもそうですが、
この赤ナメクチ間近の高巻き
(ほぼ岩場直上からの)も
危険なところだと思います。

この後はしばらく進んで巨石帯に突入し、
縫うように岩の間を、
アスレチックの如く進みます。
⑧光の輪
全体的にこの谷の滝は、
名前の付けられ方の質が高いなと感じました。
【コウリン滝 25m】

辿り着いたコウリン滝は、
ちょうど光が挿しこみ、
眩しい状態でしたが、
非常に綺麗な姿が拝めました。
林道終点から
休憩時間も全て込みで約3時間半。
ワイヤーが谷沿いに伸びてるとはいえ、
あくまで初級の沢登りとは言え、
この滝は十分に秘瀑だと思います。

うまい具合にできた影のために、
涼しさと暖かを思いのままに選択できる、
至福の条件下の滝前の大岩の上で
しばしコウリン滝に見惚れました。
⑨下山→天竜→橿原
今回はここで引き返し。
僕はここで右岸沿いに登ろうと考えましたが、
ここは友人案のそのまま引き返す
プランを選び、結果的にこれが当たりでした。

左岸沿いの道は、昇竜の滝上で道を失い、
また昇竜の滝下でも道がないので、
あのハシゴ通過が必要になります。
無事矢納滝まで戻り、
体制を整えて、最後に上多古川本谷の、
【天竜の滝】を見に行きました。

この滝と矢納滝だけなら幾分お手軽なので、
もっと訪れられて良いと思いました。
それなりの規模感で綺麗な滝でした。
橿原神宮⇒橿原ぽかぽか温泉⇒駅まで送る
と推移し、ついに1人に。
今回の遠征は、
2人も紀伊半島まで来てくれたこと。
それに尽きると思います。
限界まで攻めたか?と言えば
攻めてはいないですが、
間違いなく大切な何かが、
そしてあり得ない美しい世界が、
そこにはあったと。
それだけは間違いないと感じました。
初日、立間戸でお世話になった皆さんも
有難うございました。
アクセス
Step1 川上村上多古へ
Step2 林道終点まで行き谷沿いへ